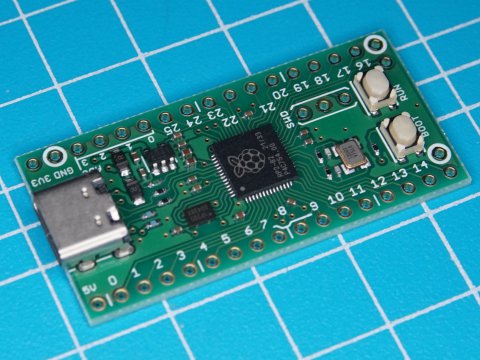自宅メールの話(UUCPの頃)
自宅で最初に電子メールが使えるようになったのは1994年頃だったか、今回はその頃の話を思い出しながら書いてみたいと思います。
私はいわゆる「パソコン通信」というものはやっていませんでした。(アマチュア無線によるRBBSはちょこっとやっていました)
大学のメールアドレスはありましたが自宅からのアクセスはできませんでしたし、修了後は使えなくなるのでそれまでに何らかの手段を用意したいと思っていました。
ちょうど386bsdを動かしていましたし、大学のメールの運用にもちょっと関わっていました。
可能なら自宅でメールサーバを運用したいと思いましたが、まだ個人向けISPが生まれたかどうかという時期です。それに接続料を払う余裕もありませんでした。
幸い知り合いに先に運用始めていた人がいたのでそこへ接続させてもらうことにしました。実はその知り合いもまた同じ方法で接続していまして......
好意で繋がせてもらったので迷惑をかけてはいけません。