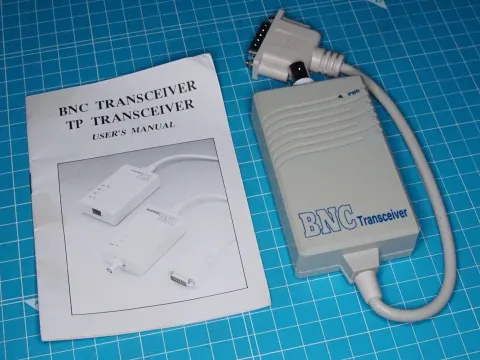EN2216も開けてみた
PCMCIAカードはたいてい両面の金属板を巻き込んでカシメてあります。これは開けようにも破壊するしかありません。
しかしEN2216はどうやら接着してあるらしく、さらに幸運なことに片側が剥がれかかっています。ヘラを挿し込んで剥がしていき、最後に残った68ピンコネクタ部分にはIPAを流しました。

ということで裏側を剥がすことができました。PCMCIAカードを開けたのは初めてです。
固定は両面テープのようなもので、古くなってパリパリになっていました。
表側も剥がしたのですが浮いている部分が見当たらず、唯一ヘラを挿し込めそうな尻尾側のコネクタ部分はコネクタが剥がれそうで……