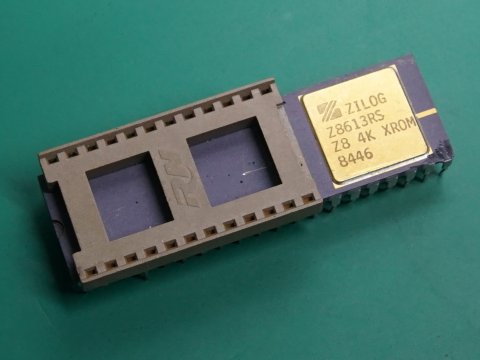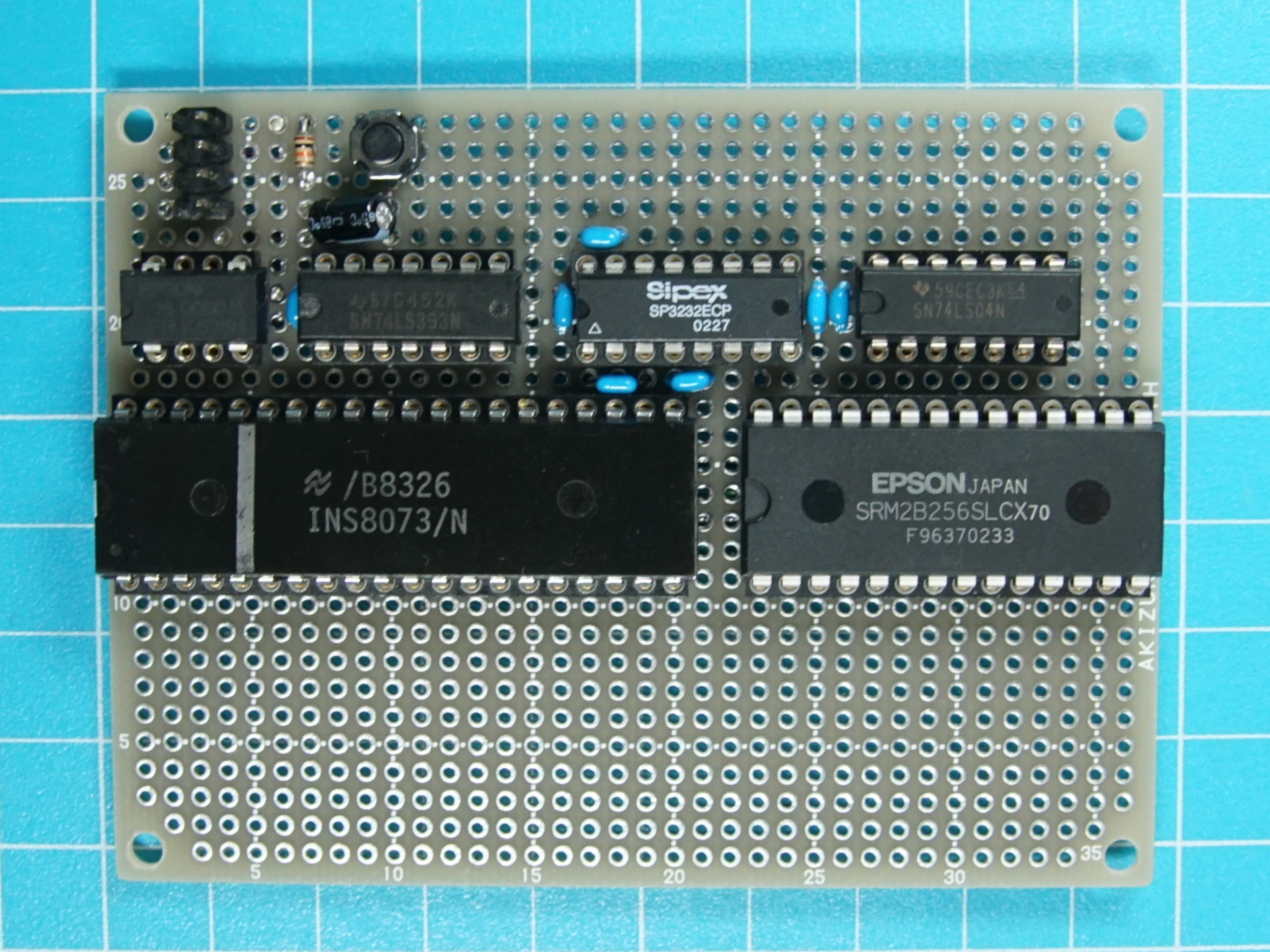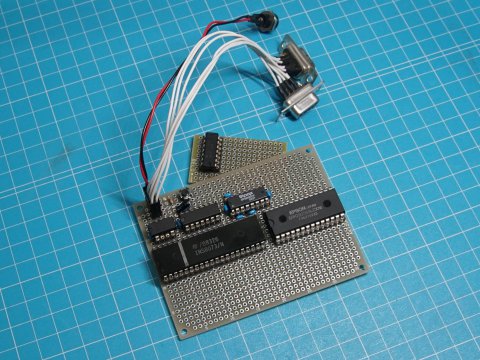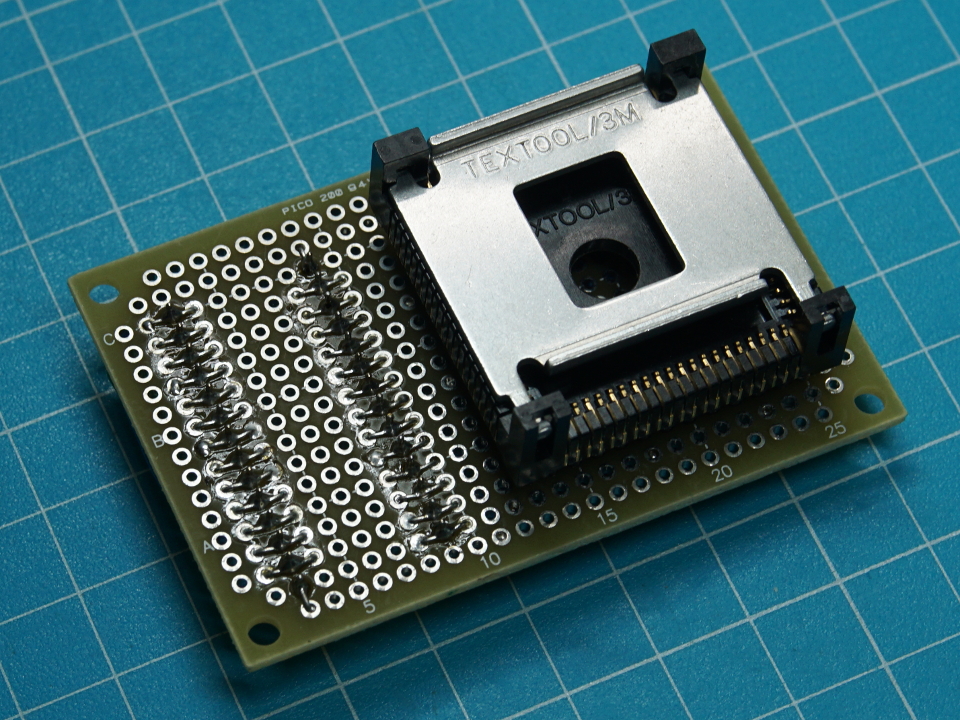Hitachi H8/338
HD6473308CP10は合計10個でてきたのでH8/330用アダプタでブランクチェックしてみたところ9つのブランク品が確認できましたが、残り1つはよく見るとHD6473388(H8/338)が混じっていました。
これがHD6473388CP10、H8/330との主な違いは以下の通りです。
- ROM: 16kB → 48kB
- RAM: 512B → 2kB
- SCI(Serial Communication Interface): 1ch → 2ch
- D/A Converter: None → 8bit 2ch
ピン配置は互換のようですが、問題はROMの容量が増えていることです。