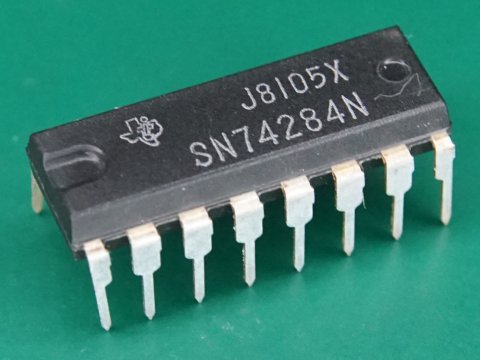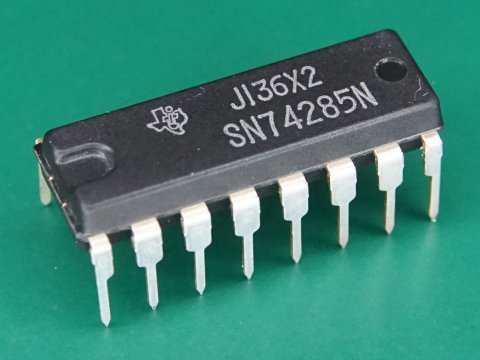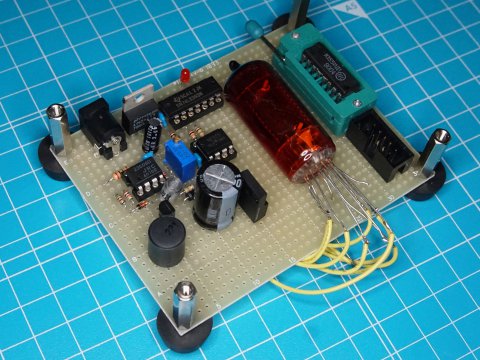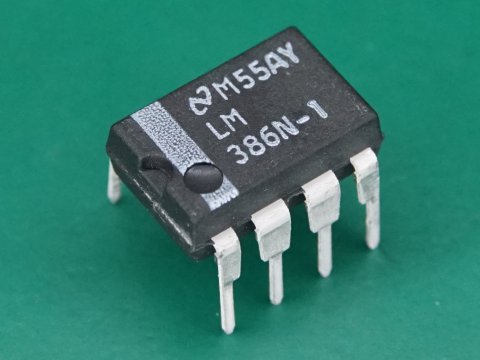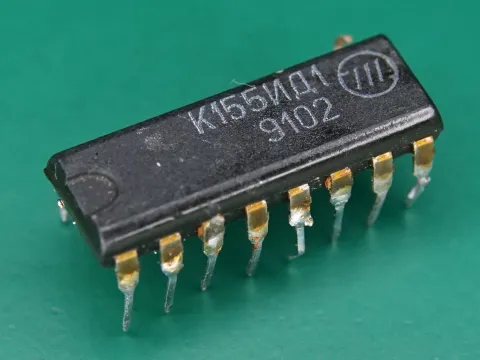SN74LS56
(ノーマルだけでなくLSやASなども含んだ広義の)74シリーズといったらどんな姿を想像しますか? 14~20ピンくらいのDIP(今だとSOICやSSOPかもしれませんが)を思い浮かべる人が多いと思います。より多い方は以前74シリーズの変り種(その3)で取り上げました。では少ない方はというと......
実は8ピンというのが2種あり、その一つがこのSN74LS56です。
これは1/50の分周器で、中に1/5の分周器が2つと1/2の分周器が1つ入っています。
ちなみにもう一つはSN74LS57という1/60の分周器です。
1/50と1/60があるということは、そう電源周波数から1秒を作るのが目的でしょうね。実際データシートにもそれが真っ先に記載されています。さらにSN74LS57を並べれば1分や1時間を作るのにも使えます。