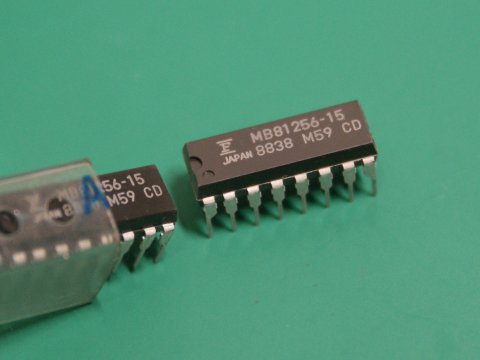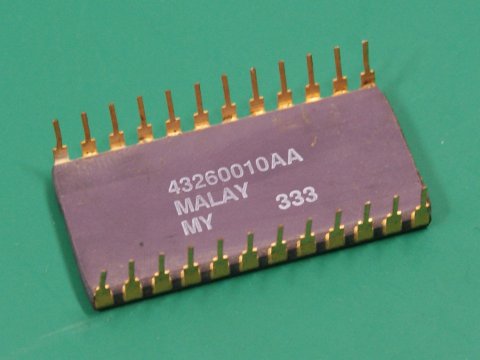NEC uPD765AC FDC
これも買っていなかったと思っていたのに、いつの間にか購入していたようです。
このμPD765AC-2はNEC製のFDC (Floppy Disk Controller)です。
Western DigitalのFD1791/FD1793 (日本では富士通のMB8877のほうが知名度が高いかな)とともに代表的なFDCです。というよりもごく初期のものを除くとほとんどのFDCはこの765系かWD系のどちらかに属すると言っても良いかもしれません。
765系はPCに採用されたこともあり、多くの派生品が生まれました。