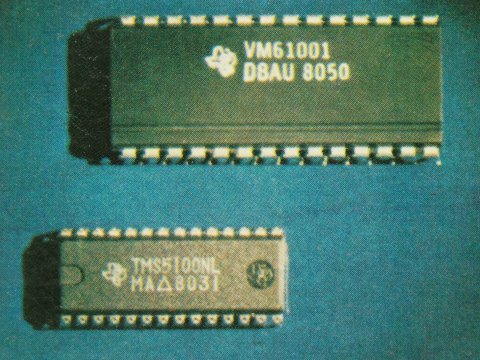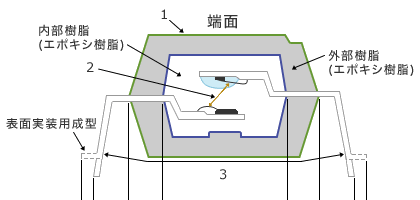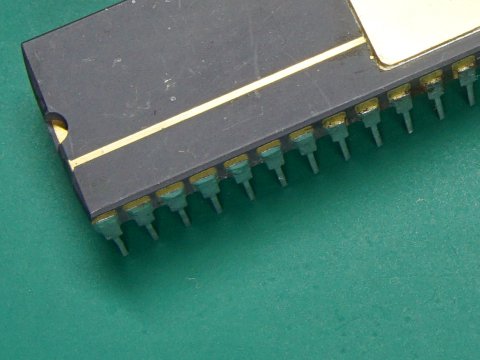サイト移行(その2)
前回に引き続きサイト移行作業について書いていきます。
最初に前回書き忘れたことを補足しておきます。いきなりデータ移行から書きましたがその前に大事な作業がありました。
それは必要なモジュール(機能拡張)をインストールして有効にしておくことです。移行しなくてはならないデータの中にはこのモジュールで定義されたものもあり、有効にしていないとそのデータが欠落してしまうためです。
まずは旧サイトで有効になっているモジュールの一覧を作成する必要があります。それを新サイトでも有効にするわけですが、基本機能(コア)に取り込まれていて有効にするだけで良いもの、同名でDrupal 10に対応したものがありインストール・有効化が必要なもの、名称が変わっていて探さなくてはならないもの、対応するものが無いもの、などさまざまです。
最初の2つは機械的にやるだけですが、名称・機能が似ていても移行できるかはまた別の話ですし、無いものはどうしようもありません。
幸いなことに絶対失いたくないデータに関するものは何とかなりました。
これらを有効な状態にして前回のデータ移行を行なったのでした。