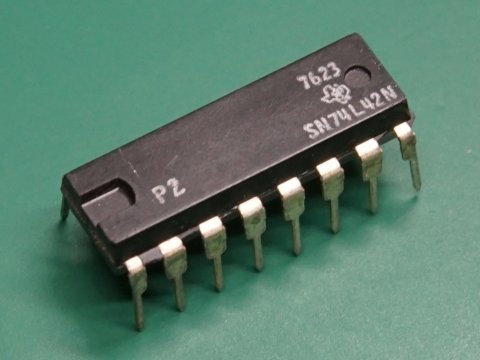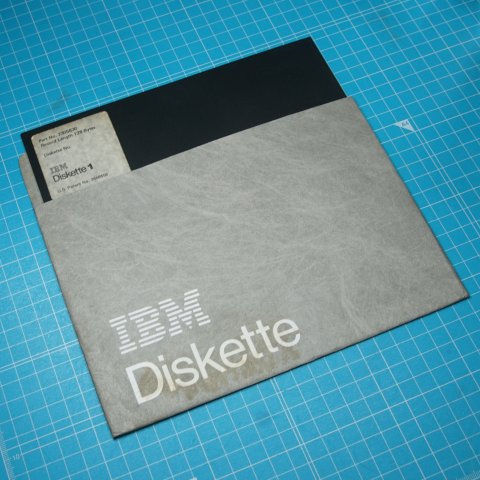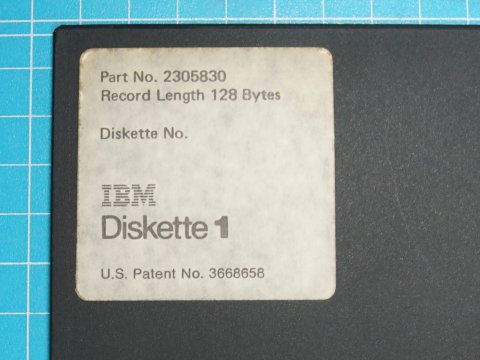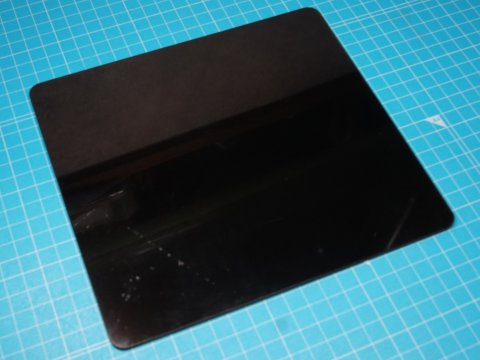MB8861 と MB8870
予告どおり富士通のMB8861, MB8870です。
MB8861はMotorola MC6800の相当品ですが、いくつか独自の命令が追加されています。これは1979年製のようですね。
パッケージは中央に大きな円と下側に溝のある富士通独特の特徴あるスタイルです。今回は国内調達したのであまり心配はないのですが、海外からだとこのパッケージは(ニセモノの可能性が低いということで)安心材料の一つといえそうです。
さて、追加された命令の詳細を知りたいところなのですが、富士通のデバイスはデータシートの入手が難しいことが多く、このMB8861も入手できていません。ハード的にはMC6800と差し替え可能ということで、「リンク」に挙げたサイトの情報と実験をもとに動かしていきます。