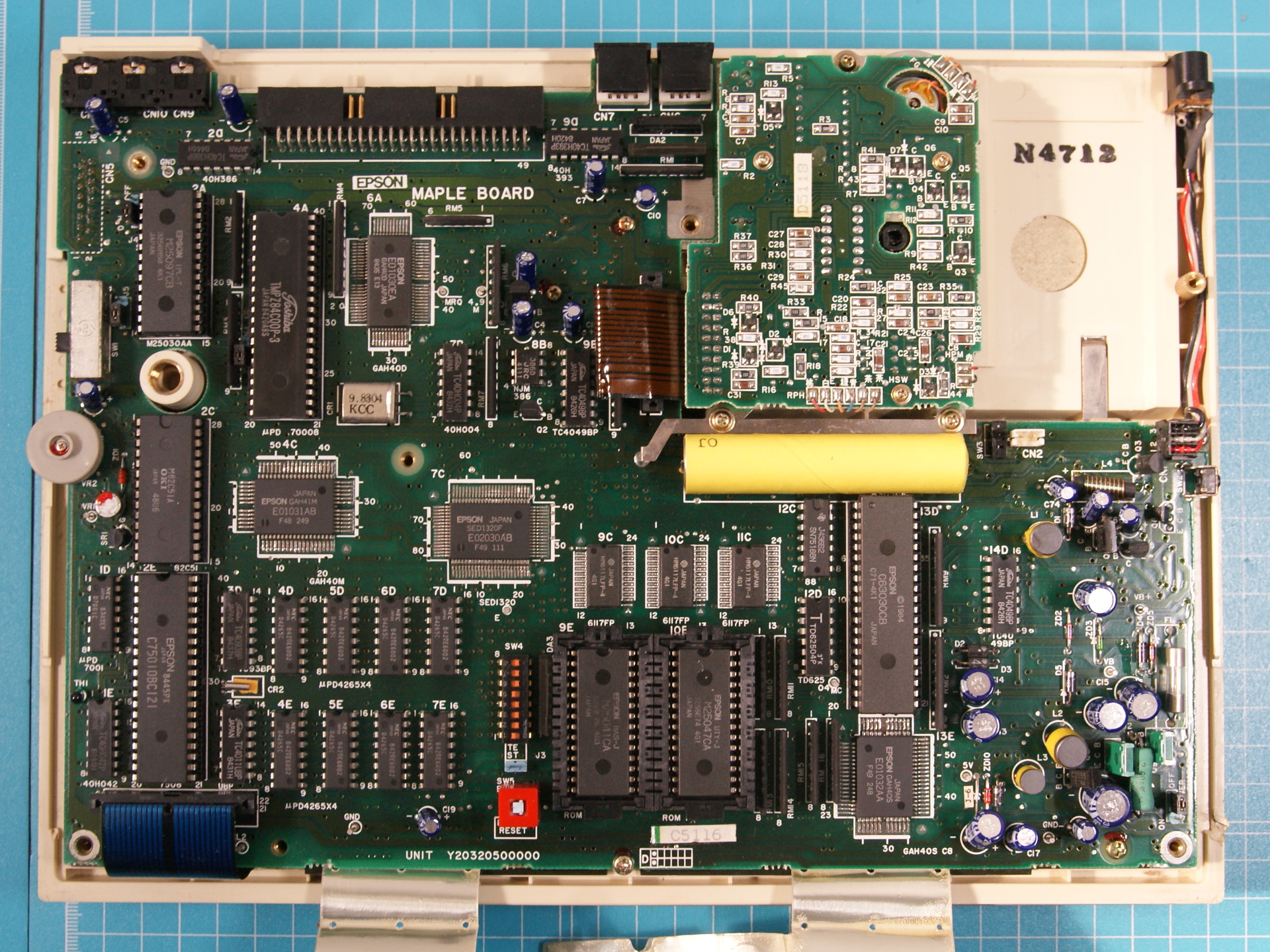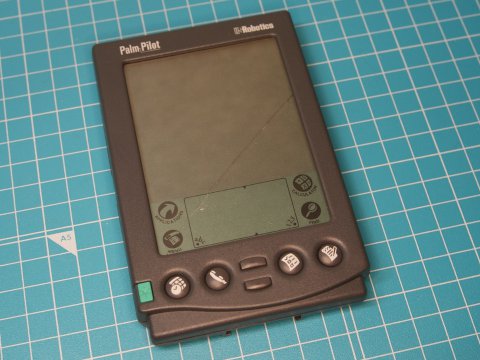金属探知機 WP105
昔なんとなく面白そうで買ってしまったものの、案の定使用する機会はまったくありませんでした。
COLLUCKで検索するとテスターなどを作っている会社みたいですね。「WIRE AND PIPE DETECTOR」とありますからリフォーム等の際に壁の中を探るためのものでしょう。
手前側を握って使います。赤と緑のLEDは電源と検知を示すもの、赤いツマミは感度調整です。
スライドスイッチは○と△を選択するようになっていますね。
写真奥の側を壁に向けて使用しますが、「○ DETECT」「△ DETECT」と書かれていて検知する範囲が示されています。先ほどのスイッチはこれを切り替えているのでしょう。