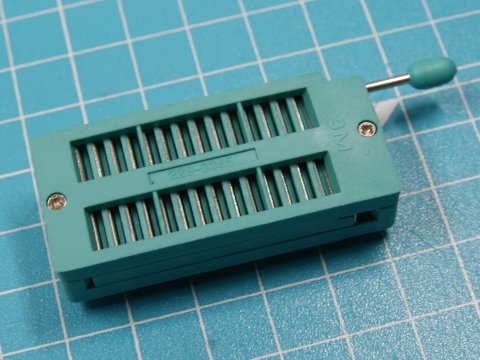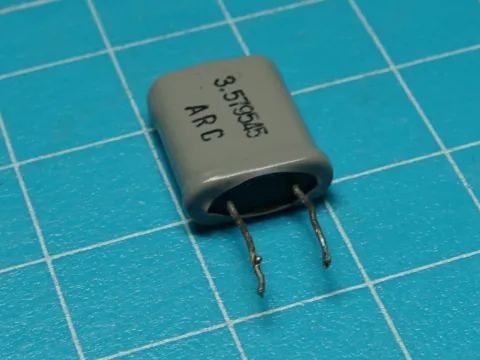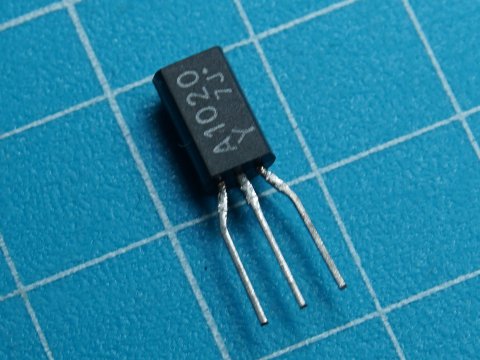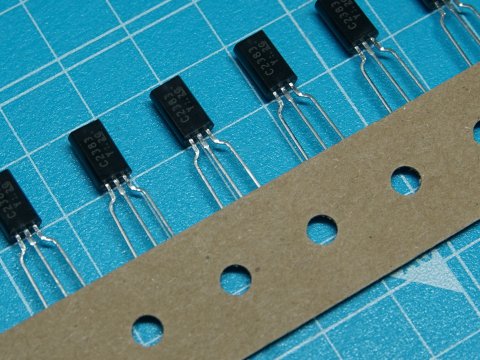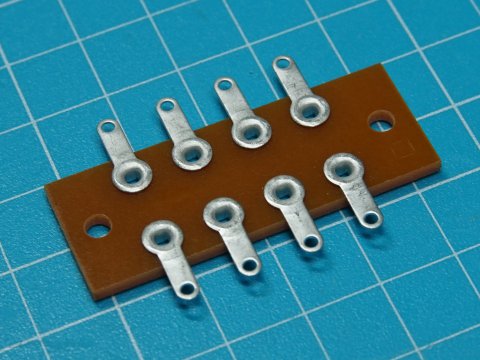日本を変えた千の技術博(前編)
国立科学博物館は以前訪問していますが、企画展目当てに行ってきました。「明治150年記念 日本を変えた千の技術博」、3月3日までの開催です。
例によって電気関係の展示をいくつか紹介していこうと思います。今回は計算機以外です。
これはコヒラー検波器(コヒーラ検波器・コヒーラ管とも)と呼ばれた初期の検波器です。ガラス管の2つの電極の間に金属粉が封入してあり、電波を受けると抵抗値が下がります。電波が無くなってもそのままでは元に戻らないので、機械的に衝撃を与えるなどしてリセットする必要があります。
このような特性なので当然のことながら電信にしか使用できません。
これ子供のころ愛読していた図鑑に載っていたのを憶えていますね。