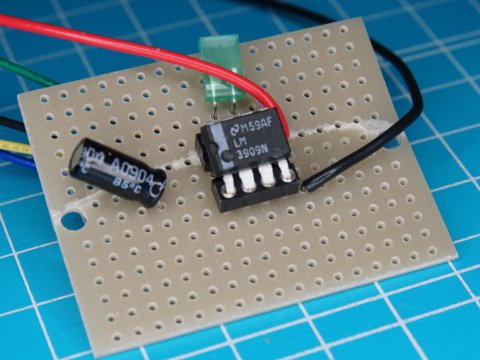今は無きモノ(その他編)
カテゴリー:
4回目はその他編ということでこれまでの工作・電卓・コンピュータのどれにも分類できなかったものを取り上げます。
- ターミナル
まだ晴海で開催されていた頃のハムフェアで手に入れたターミナル(シリアル端末)です。最終日の夕方、持って帰るのが面倒になった出展者がタダで配り始めたのを貰ったんだったかな。
オレンジ色に塗装された鉄製ケースに基板とキーボードが入っていました。ディスプレイは無く(専用品が存在したのか汎用品を接続する前提なのか不明)M型コネクタでビデオ信号が出るようでした。開けてみると基板上にCPUの類は無く汎用ロジックICが並んでいたのを憶えています。UARTくらいは載っていたかもしれません。
かなり大きくて重かったのを頑張って電車で持ち帰ったのか、知り合いのクルマに載せてもらったんだったか、記憶にありません。タダだったから貰ったものの特に必要とする状況は無くそのままになっていましたが、やはりこれも改築時に処分してしまいました。