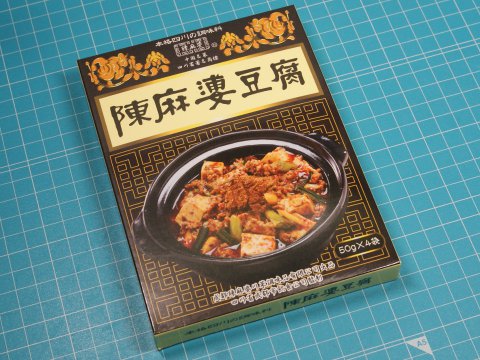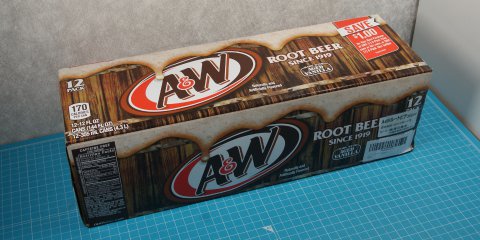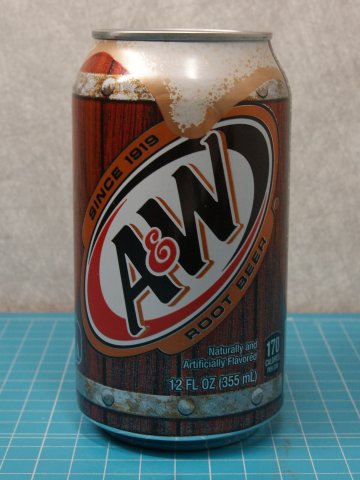SASボードらしきもの
前から気になっていたボードを買ってみました。
場所は秋葉原のラジオデパートの地下、随分前からあったのですが売れる気配が無いので様子を見ていました。でも1枚たったの500円なので...
どちらもホストインターフェイスはPCI Express、カードエッジは×8対応のピン数です。カードエッジ部のパターンを見る限り電気的には上のものは×8、下のものは右半分が配線されていないので×4と思われます。
上のボードではブラケット部にSAS ×4の外部接続用のSFF-8470と思われるコネクタが、基板右にはやはりSAS ×4のSFF-8484と思われるコネクタが装備されています。
下のボードはブラケット部にはコネクタは無く、右端にMini SAS ×4のSFF-8087らしきコネクタが2つあります。