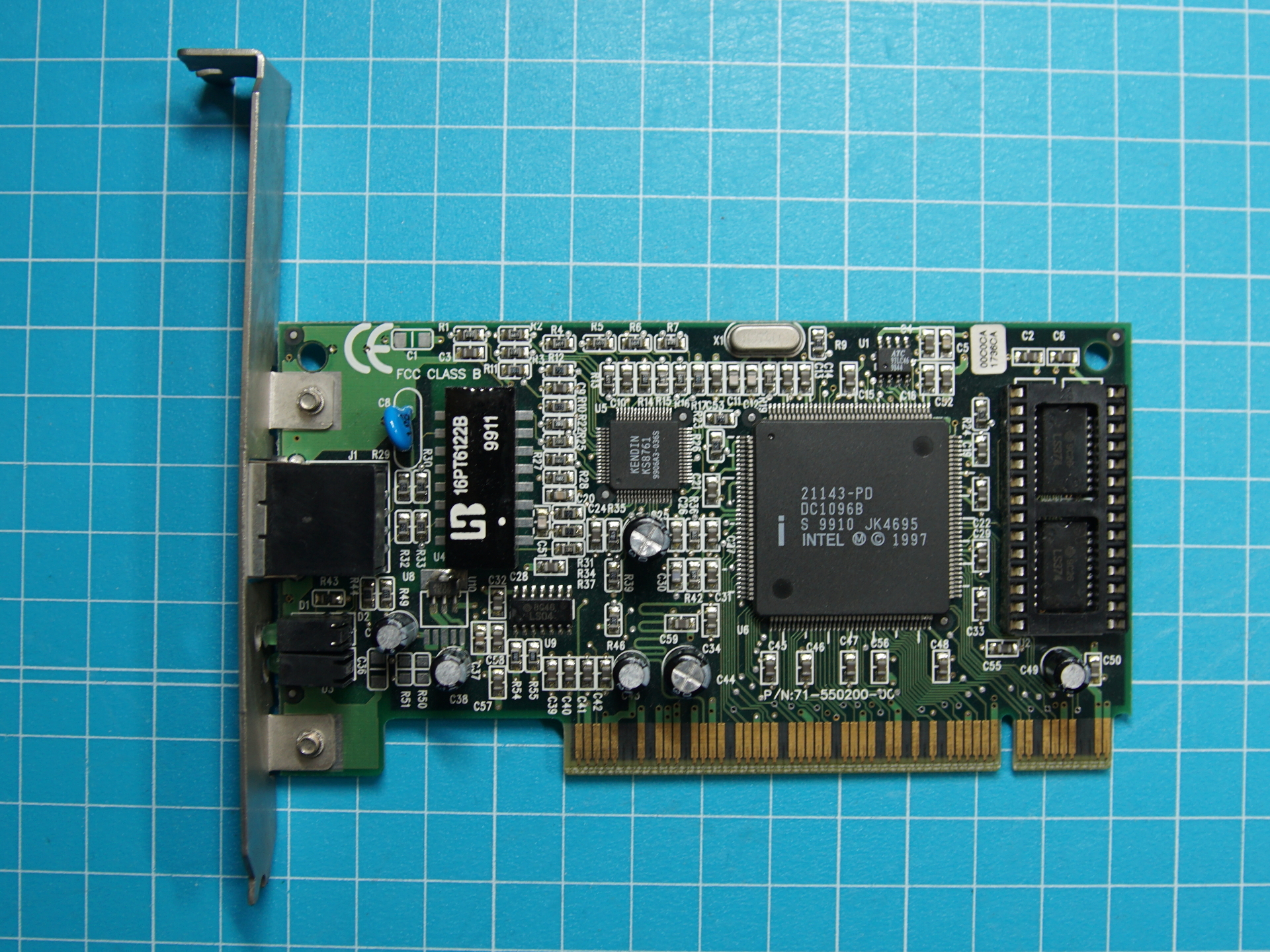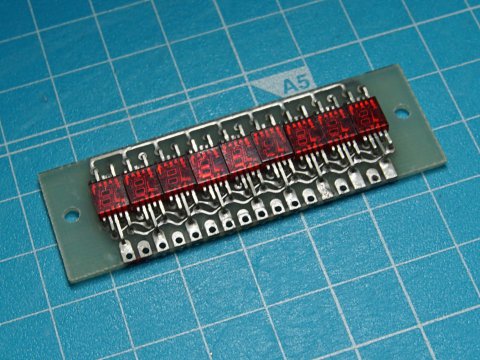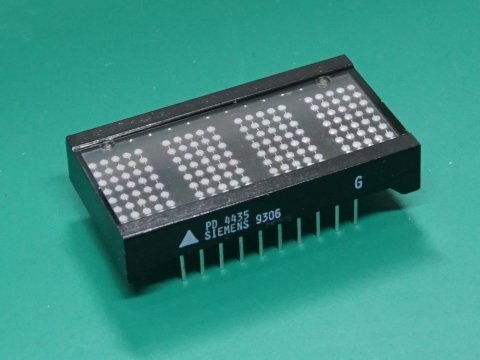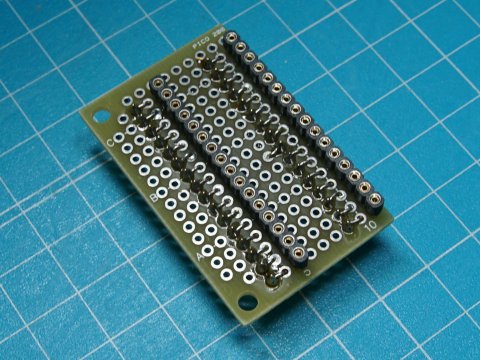GAL22V10
前にGALとCPLDのGAL16V8を取り上げましたが、GAL22V10もいつの間にか買っていたようです。
LatticeのGAL22V10B-25LPです。「-25」はPropagation Delayが25nsのもので、GALの中では最も遅い部類になります。
GALには主に16V8, 20V8, 22V10の3種類がありました。
GAL16V8は20ピンPALの16L8, 16R4などの置き替え用です。PALでは出力の形式(負論理の「L」、レジスタの「R」など)によって品種が分かれていましたが、GALではプログラマブルにすることによって品種の集約を図っているのです。さらにPALには存在しない組み合わせも可能になっています。
GAL20V8は同様に24ピンPALの20L8, 20R6などの置き替え用です。