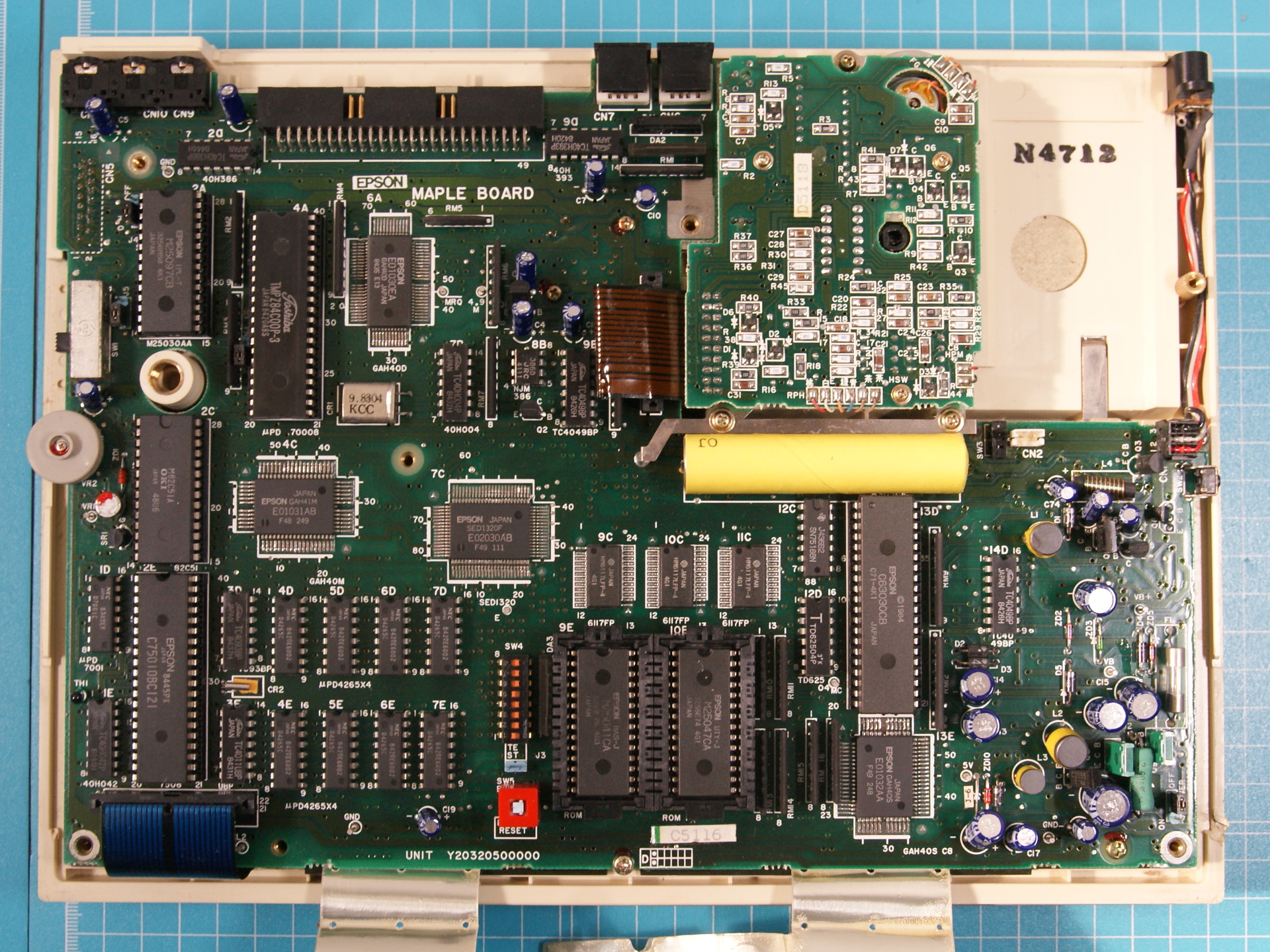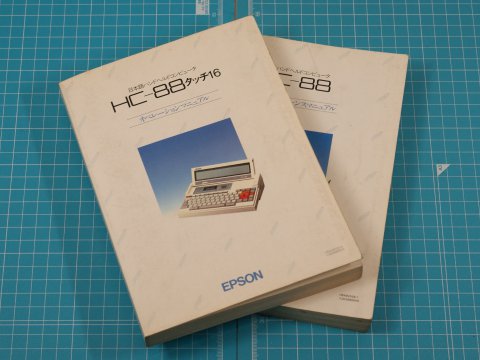ThinkPad X60用にHDDを買ってきました
ThinkPad X60のHDDの調子がおかしいので交換用にHDDを買ってきました。
これが買ってきた東芝のMQ01ABD100です。これまでのものは500GBだったのですが、500GBと1TBで値段があまり違わなかったので1TBに増量です。2つあるのはちょっと別の予定があるから(先日の超小型PCではありません)です。
超小型PCで4096バイト/セクタのHDDでも何も問題ないことがわかったので「ADVANCED FORMAT」のものです。もっともこの容量で512バイト/セクタのドライブは無いと思いますが...